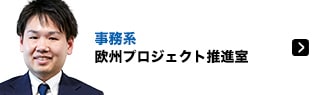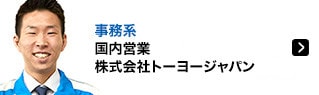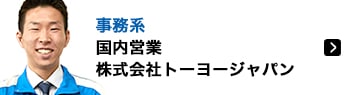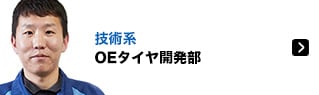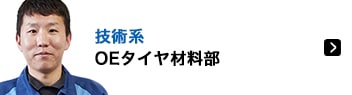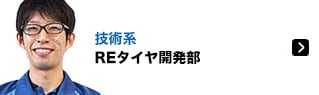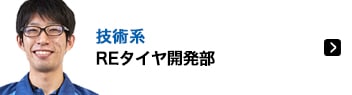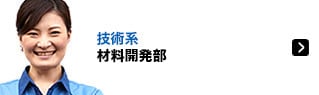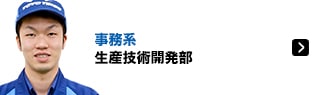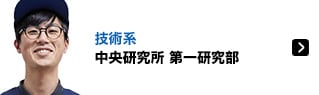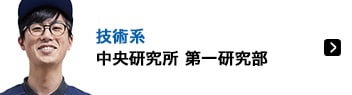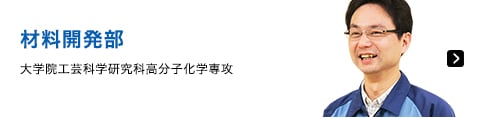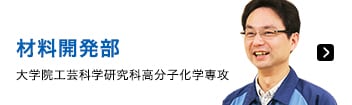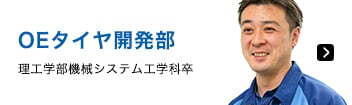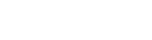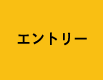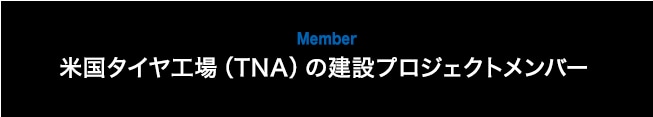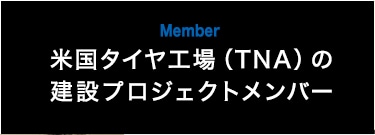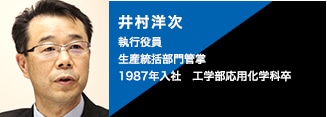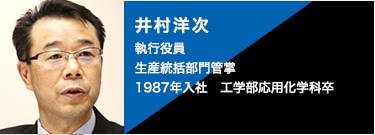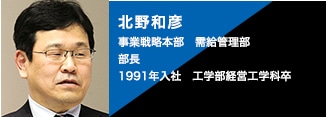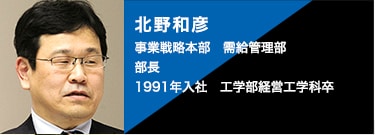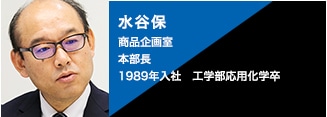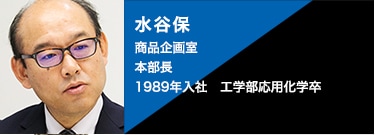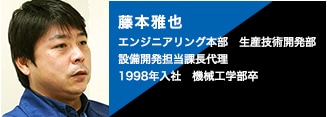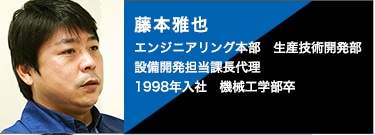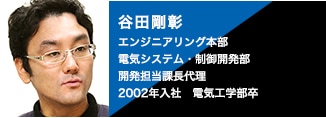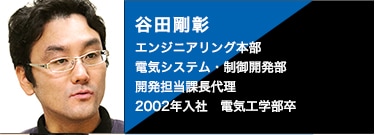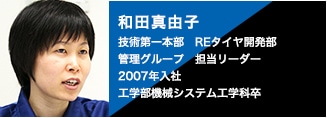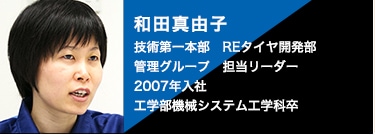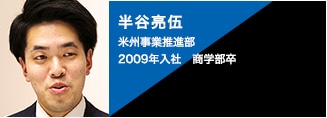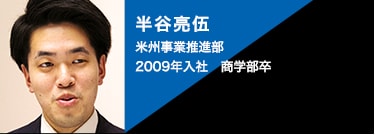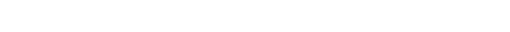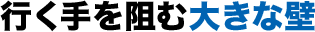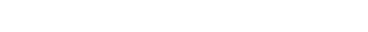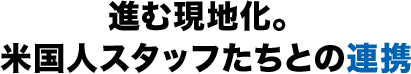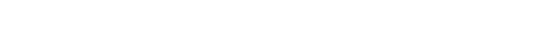- TOP >
- プロジェクト >
- プロジェクト No.2「米国タイヤ工場(TNA)」 >
- Project Story

アメリカに新工場をつくろう——。そんな話が最初に持ち上がったのは、2000年代初頭。米国の販売子会社から「近い将来、北米市場でスポーティなSUVやCUVがブームになる」とのマーケティング調査の報告が寄せられたのがキッカケだった。当時「TOYO」ブランドの大型車向けタイヤは品質の高さで知られ、北米市場で高い評価を獲得し、信頼性のあるブランドとして多くのユーザーの支持を集めていた。そのブランドイメージを活かし、市場ニーズの変化にいち早く対応した新商品を開発し、新工場を通じて北米市場に供給すれば、新たなマーケットを切り開くことができるに違いない——。TOYO TIREはそう判断して、北米新工場建設を決断した。プロジェクトに最も初期の段階から参画し、プランニングなどを手がけた北野和彦(現SCM本部需給管理部長/1991年入社)はいう。「その当時、販売が拡大していた北米大径/大口径タイヤの供給能力増強が急務ということで製造・販売・技術がひとつになった全社プロジェクトがスタートしたんです」(北野和彦)。
社内には、異論もあった。マーケティング調査の分析が正しいかどうかは、誰にも分からない。もし間違った見通しであれば、ダメージは計り知れない。だが結果として、当時のその判断は正しかった。その後、予想した通りにSUV/CUVの世界的なブームが起き、TNAは増産に次ぐ増産。これを足がかりに、TOYO TIREは新たな飛躍を遂げたからだ。当時を知る井村洋次(現生産統括執行役員/1987年入社)はいう。「その頃のTOYO TIREは同業他社と比べて国内生産比率が高く、海外に自前の工場もなかった。それだけに新工場の話を聞いた時は、『いよいよやるか』と、たかぶるような思いでした」(井村洋次)。井村だけではない。他の多くの社員も、北米工場建設の決断を前向きに受け止め、新たな意欲を燃やした。TNA建設プロジェクトは、社内の期待を一身に集めて動きだした。




新工場建設が正式発表されると、タイヤ設計部門、生産技術部門、製造部門など各部署から社内横断的に技術者を集めてプロジェクトチームが編成され、専門チームに分かれて新工場の生産品目や導入設備の検討作業が始まった。一方現地では、2004年10月から本格的な建設工事がスタート。翌年建屋が完成すると、生産設備立ち上げや量産ラインの構築、現地スタッフの指導育成など、本番稼働にむけた準備のために総勢100名を超える技術者や現場の製造スタッフが海を渡り、次々と現地入りした。その多くは、海外での業務経験など一度もない。あわててパスポートを申請するスタッフも少なくなかった。現地では、珍事も起きた。工場敷地の地下で鍾乳洞が見つかり、一部で工事をストップせざるを得なくなったのだ。その影響で原料となるゴムの製造が困難になり、代替品を調達するために技術者が全米を走り回る一幕もあった。
生産設備の立ち上げは、困難をきわめた。事前に国内工場で入念な準備を重ね、ほぼ完成に近い状態で設備を現地に持ち込んだものの、原材料の特性や動作環境の違いで不具合が生じ、現地での調整に手間を要した。人の問題もあった。生産設備を実際に動かし、モノづくりにあたるのは現地採用の米国人スタッフだが、ほぼ全員が未経験者。製造現場を知り尽くした国内工場の熟練作業者が指導にあたるが、習熟するのに時間がかかる。だがその壁を乗り越えるのに、多くの時間は必要なかった。時間の経過とともに信頼関係が生まれ、言葉や習熟の壁を越えて、スタッフが一丸となり仕事に励むようになった。「是が非でも新工場を立ち上げたい」。そんな思いを誰もが共有し、気持ちをひとつにしていた。量産ラインから最初の試作1号タイヤが出てきたのは、本番稼働を3ヶ月後に控えた2005年10月。「涙が出そうになるくらい嬉しかった」。専門チームのリーダーとして現地に赴任していた井村は、この時の感動をそう表現する。

2006年1月から本格生産を開始したTNA。翌2007年には、早くも「第2期」のプロジェクトがスタートする。「第1期」では、ピックアップトラックやSUV向け市販用タイヤの生産に限定されたが、「第2期」では国内工場から技術移転して新たに自動車メーカー向け純正タイヤの量産を立ち上げ。同時にスポーツカー向けのハイパフォーマンスタイヤ(UHP)の生産設備を新たに導入するのが「第2期」のテーマだった。
だが純正タイヤの量産立ち上げには、多くの時間と手間を要した。国内工場からの技術移転とはいえ、工法の違いからくる仕様変更や、高い要求性能に対応した作りこみに時間を要した。当時タイヤ開発部で純正タイヤの設計を手がけ、量産立ち上げのリーダーとしてプロジェクトに参加した水谷保(1989年入社)が当時を振り返る。「生産効率を高めようとタイヤ部品の製造プロセスを短縮する新技術に挑戦したのですが、プロセスを短縮した分だけ安定性が損なわれ、歩留まりが低下するというジレンマにずいぶん悩まされました。しかも試作品を評価する走行テストを、当時は日本でしか行なえないという事情もあって時間のロスもあった。現場の米国人スタッフに日本の自動車メーカーの要求レベルの高さを納得するまで説明し、何度も試作を重ねては改善するという繰り返しの中で解決するしか方法はありませんでした」(水谷保)。最終的に自動車メーカーから量産化の承認を得るまでに想定以上の期間を要した。

TNAは、さらに「第3期(2010年)」「第4期(2013年)」と、数年ごとに生産能力増強のための拡張工事が実施され、規模を拡大していった。初年度月産で1万本程度の時期もあった生産量は、2011年8月には年産650万本にまで拡大。第4期が完了した2015年8月には、さらに年間250万本の生産能力が追加され、北米市場向け製品の一大供給基地へと発展を遂げた。
継続的に行なわれるプロジェクトは、技術者にとって絶好の成長の機会でもあった。第1期から第4期までのすべてのプロジェクトに関わり、TNAとともに成長を遂げた技術者も少なくない。生産技術開発部の藤本雅也(1998年入社)も、その一人だ。「いちばん印象に残っているのは、プロジェクトの第3期。材料工程の設備立ち上げに主担当として関わり、生産時間の短縮にむけて新たな生産プロセスを考案し、設備自体も大幅に設計改良したんですが、TNAにむけて送り出す直前の検証で不具合が見つかり、現地で対応するのに四苦八苦しました。もし現地の仲間たちの協力がなければ、一人では問題解決できなかったでしょう」(藤本雅也)。そんな苦い体験を通じて、藤本は「あきらめない強さ」を学んだという。「現地にいると、時差の関係で日本の上司の指示を仰ぐ時間もなく、その場で問題解決しなければいけない場面が多々あります。そんな中で、自分の力でなんとかしなければという強い気持ちを持てるようになりました」。プロジェクトが始まると、半年ほど日本を留守にする。帰国すると、今度はマレーシアや中国の工場に出張。「1年の半分は海外」というほど多忙な日々を過ごす中で、今では外国人とも自然体で接することができるようになった。


藤本と同じ生産技術開発部に所属する谷田剛彰(2002年入社)の場合は、入社3年目で第1期に参加。その後第4期までのすべてのフェーズに電気担当技術者として関わった。プロジェクトメンバーの一人としてアメリカ行きを告げられた時は、てっきり先輩の“補助要員”と思ったが、現地に到着して3ヶ月後、いきなり前工程(原料混合)の設備立ち上げを任された。「まったく経験がないので、不安だらけでした。でも任された以上は責任を果たしたいという使命感が自分の中に生まれて、それからは死に物狂いで頑張りました」(谷田剛彰)。また、すべてのフェーズに参加できたことにも大きな意味があったと谷田はいう。1度目の渡米では分からなかったり、疑問に感じる課題があっても、2度3度と現地を経験するうちに次第に理解できるように分かるようになったこともあったからだ。TNAプロジェクトは、生きた知識を学ぶことのできる“学校”でもあった。

TNAは、当初、日本から設計・開発の技術者や現場作業者が大挙して現地に入り、米国人スタッフを指導育成しながら量産立ち上げまでを指揮監督するのが通例だった。だがフェーズを重ねる中で少しずつ現地スタッフも育ち、「第4期」では米国人スタッフがプロジェクト推進の中心的役割を担うまでに現地化が進んだ。REタイヤ開発部の和田真由子(2007年入社)が「第4期」のメンバーとして渡米した時も、同じ設計部署の技術者で現地赴任したのは和田一人。実質的なリーダーでもあった。「私が担当したのは、ライトトラック向けの市販タイヤの量産設備立ち上げです。この頃になると設計開発も現地化が進んでいて、新たに量産するタイヤもTNAに常駐する米国人のエンジニアと連携して設計したものでした。またこの時は工法も設備も新規に導入するもので、私にとっては初めての経験でした」(和田真由子)。

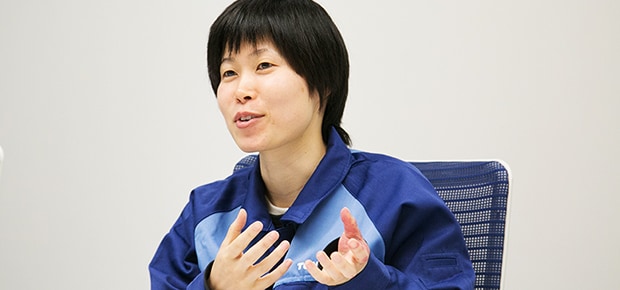
和田が現地入りするのは、「第3期」での2度の渡米についで3度目。慣れもあって技術面で苦労したことはほとんどなく、むしろ日米の文化の違いを目の当たりにして戸惑うことが多かったという。「米国人は定時(午後5時)になると、さっさと職場を離れて家路を急ぎます。決して「いい加減」というわけではなくて、5時までに仕事を終えるにはどうすればいいかを考える。そこが日本とのいちばんの違いですね。また効率を最優先に考えて、ムダだと思うことがあると質問攻めにしてきました。それで苦労したことは1度や2度ではありませんが、日本の会社の仕事の進め方を振り返るといろいろと考えさせられることは多いし、勉強になることも少なくありません」(和田真由子)。日本にいては絶対に学べないことを、TNAのプロジェクトを通じて学ぶことができたと和田は思っている。

TNAは「第4期」が終了し、新たなステージに入っている。2017年から「第5期」がスタートしたのだ。第5期は、約140億円の巨費を投じて年産240万本の生産能力持つ新工場を建設するというもの。2019年4月の稼働をめざして、具体的なプランの検討が始まっている。完成すれば生産能力は大幅に増強され、市場への製品供給能力も格段に向上する。社長直轄の北米事業推進部で新製品の開発や内外の工場との生産調整にあたる半谷亮伍(2009年入社)はいう。「TOYO TIREは、中国、マレーシア、タイにも工場を展開していますが、中でもTNAは収益に対する貢献度が高く、事業戦略を推進する上で最も重要な生産拠点に位置付けられています。それだけに『第5期』のプロジェクトは全社を挙げて大きな期待を寄せ、2019年4月の稼働にむけて新工場でどんなタイヤをつくるべきなのか、米国法人や製品開発部門とも連携しながら商品戦略を検討しているところです」(半谷亮伍)。



北米市場は、世界中のタイヤメーカーがしのぎを削る競争の舞台でもある。現在TOYO TIREは、その北米市場でシェア第7位。これをさらに第5位までランクアップする礎を築くことが中期計画で大きな目標のひとつに掲げられている。その正否のカギを握るのは、「第5期」のプロジェクトだと半谷はいう。「中期計画では、収益体質の強化も大きなテーマです。それだけに、ただ単に生産規模を拡大すればいいというものではなく、質をともなった成長を遂げていかなくてはなりません。そのために何をすべきか。米国法人やTNAとも密接に連携しながら、道筋を探っていきたいと思っています」(半谷亮伍)。社内の期待を一身に集める「第5期」のプロジェクト。それを動かしていくのは、これを読んでいるみなさんかもしれない。
▲ページTOPへ