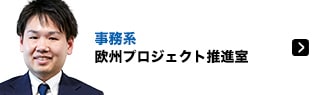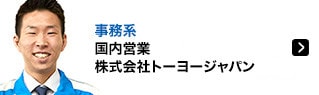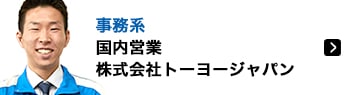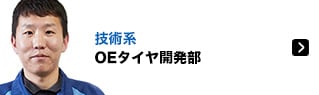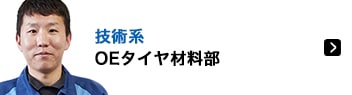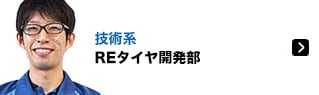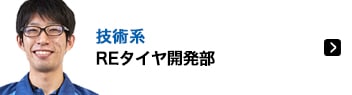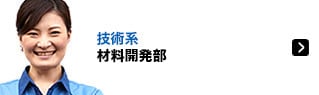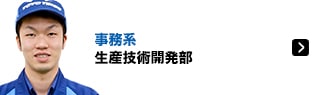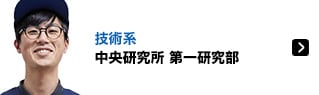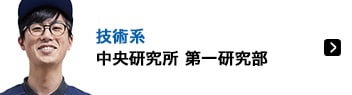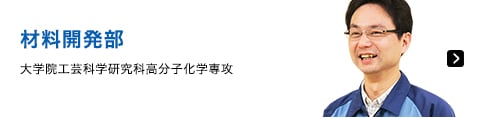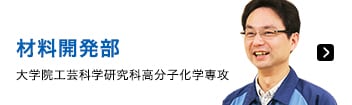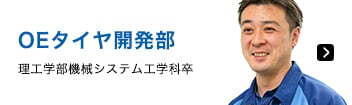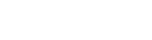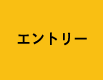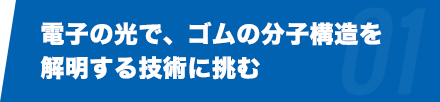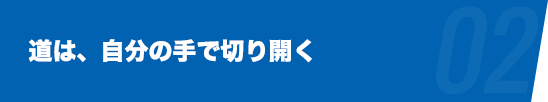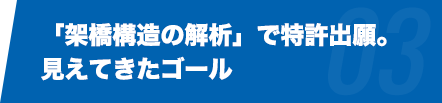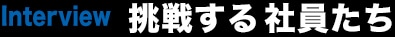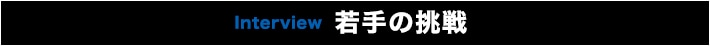- TOP >
- 社員インタビュー >
- 中央研究所 第一研究部

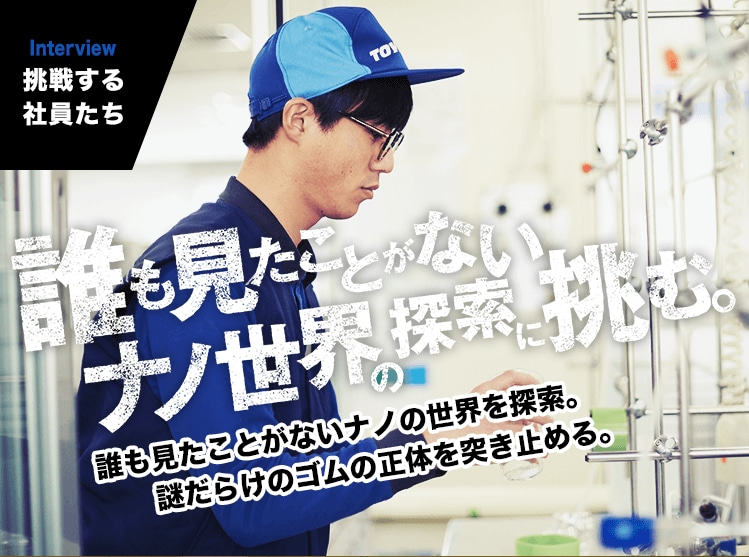 中央研究所
中央研究所
第一研究部
2013年入社
物質系工学専攻
第一研究部
2013年入社
物質系工学専攻
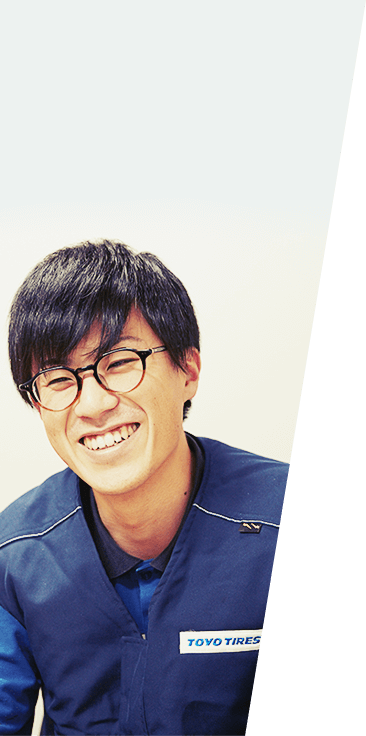

タイヤに使われるゴム材料は、カーボンやシリカ、硫黄など、様々な化学薬品をブレンドしてつくります。しかしナノレベルで見ると未解明な部分も数多く、材料開発では技術者の経験値に頼る部分も少なくありません。私が入社1年目から4年間、一貫して取り組んできたのは、そんな謎に満ちたゴムの正体をナノレベルで解き明かすための研究。光の速度近くまで加速された電子が放つ放射光を使って、ゴム材料の分子構造をナノレベルで解析する技術を確立し、最適な分子構造を持つゴム材料のシミュレーションや設計開発への応用をめざしています。成功すれば、ニーズに即した、より高性能な自動車用タイヤを短期間で開発し、スピーディーに市場に送り出すことが可能になります。製品のさらなる品質向上や、従来のワクを超えた革新的な製品開発のキッカケにもなるでしょう。
放射光を使った分析技術との出会いは、大学4年生の時。大学院でも研究を続け、いつの間にかその面白さにのめり込みました。今の仕事は、そんな学生時代の知識と経験を存分に生かせる仕事。好きな研究を仕事にできることに喜びを感じます。今まで見ることができなかったナノレベルでのゴムの構造解析は、誰も足を踏み入れたことのない未知の世界の冒険といっても言い過ぎではありません。そしてそれは、私にとって、いまだかってない大きなチャレンジです。
▲ページTOPへ


誰も知らない世界をのぞいてみるのは、たやすいことではありません。研究は、試行錯誤の連続です。例えば通常の分析機器ではナノレベルの分子構造を観察できないため、実験は外部の施設、特に世界最高性能放射光を生み出すことのできる大型放射光施設「SPring-8」(兵庫県・播磨科学公園都市)に独自の装置を持ち込んで行なっています。外部施設なので頻繁に実験を行なうことができず、限られたチャンスの中で最大の成果をあげるために、周到な実験のプランづくりと準備が欠かせません。また経験者や有効な知見を持つ研究員がいないので、研究が行き詰まった時、第三者のアドバイスやサポートを受けることができません。進む道を自らの手で切り開いていくしかないのです。
そこで世界中のあらゆる文献にあたるとともに、関連する学会にも積極的に参加し、共同研究を行なう大学や研究機関をたびたび訪ねて、最新情報の収集に努めています。また研究で成果があがっても、それが実際の業務と結びつかなければ何の意味もありません。そこで材料開発部門をはじめ、シミュレーションの専門部署や分析部門など、社内の関係部署と緊密に連携をとり、意見交換を密に行なうように心がけています。研究室に閉じこもっていては、独りよがりな研究になりがち。研究室を飛び出して、様々な意見や声に耳を傾けることが、研究を成功させる上で大切なことです。
▲ページTOPへ


スタートして4年。多くの壁に行く手を阻まれながらも、研究は着実に前にむかって進んでいます。その成果のひとつが、ゴム内部の高分子が硫黄によって結合した「架橋構造」を放射光を使って分析する新たな技術の開発に成功したことです。2016年4月には特許を出願し、2度の学会発表も行ないました。今まで誰も見たことがなかったゴムの構造の一端を、自ら考案した独自の手法で可視化することができて、これからの研究にむけて確かな手応えを感じました。
また2016年11月には、これまでの研究成果をまとめてプレスリリースも行なわれました。自分の携わった研究がTOYO TIREの名で公式に社会に向けて情報発信され、多くの人の知るところとなったのは研究員としてこの上ない喜びでしたし、研究に対して会社から一定の評価をもらえたことは大きな自信にもつながりました。でも研究が、これで終わったわけではありません。ゴムは、ナノレベルで見ると架橋構造以外にも、様々な構造を有しています。放射光を用いて、それらを分析する技術を新たに見つけ出していかなければならないし、何より実際の製品開発に生かすレベルにまで到達するには、もう少し時間がかかります。ゴムの正体を突き止める研究は、これからも続きます。
▲ページTOPへ


学生時代、マイカーのタイヤを交換し、劇的に燃費が改善されたのがキッカケで自動車用タイヤに興味を抱き、タイヤメーカーを志望。あえて最大手を避け、学生時代に学んだ知識と経験を活かした研究ができるTOYO TIREを選択。1年目から放射光を使ったゴム材料の構造解析研究を担当。2016年4月、「架橋構造の解析」で特許出願。
| 8:50 | 出社 |
|---|---|
| 9:00 | メールチェック |
| 10:00 | 大型放射光施設「SPring-8」での実験結果を整理し、データを解析 |
| 11:00 | 学会見学を明日に控え、関連資料に目を通す |
| 12:00 | 昼食。仕事のことは忘れて、頭を冷やす。ふとアイデアが浮かぶことも |
| 13:00 | 次回の実験にむけて、配合を変えた様々なサンプルを手作りで作成 |
| 14:00 | 材料開発部門に出かけて、情報交換。何気ない会話の中でヒントが見つかる |
| 15:00 | 最新の論文に目を通す。情報収集は、欠かせない仕事 |
| 16:00 | 共同開発している大学の先生に電話で連絡。研究の進捗について確認 |
| 17:00 | 同じチームの先輩研究員とミーティング。実験のプランを相談 |
| 18:00 | 退社 |
実験結果のデータを克明に記した「実験ノート」。これまでの研究活動のすべてが詰まった大切な資料。これがないと、仕事にならない。パソコンとともに、手放せないツール。
▲ページTOPへ