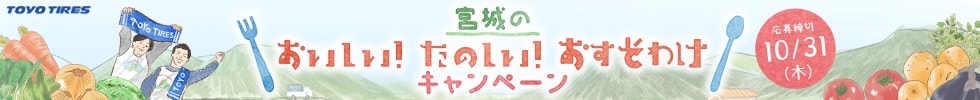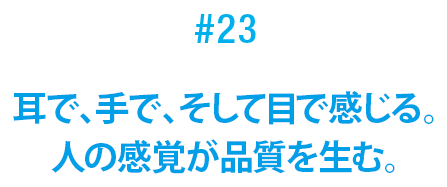-



宮城県気仙沼市最知 フカヒレ生産者
遠藤守さん
尾ビレ、背ビレ、胸ビレ、腹ビレ…。鮫にはいろんなヒレがありますが、すべてが「フカヒレ」と呼ばれます。
(株)中華高橋水産には2つの加工工場があり、加工品も作っていますが、私が担当している最知の干し場では、尾ビレを丸ごと天日で干した「丸干」を作っています。
身を切るような山風「室根おろし」が吹く11月末から4月末が干しのシーズン。この間に70~90日かけて乾燥させます。
まず仕入れたヨシキリザメやアオザメの尾ビレを平台に置いて表面を乾かします。初めから吊り干しをしてしまうと、フカヒレのウリであるコラーゲンやコンドロイチンが流れ落ちてしまうため平置きにするのですが、均等に干すためには毎日ひっくり返すという地道な作業が重要なんです。その後、重しを乗せ「そり」をなくして水分を表面に浮き立たせる安醸(あんじょう)という作業を行ないます。そして最後に吊り干しして、表面蒸発と内部拡散を繰り返す。10年もこの仕事をしていると、吊るしておいたヒレ同士のぶつかる「カラン、カラン」という音色で完成度を見極められるようになります。フカヒレの声に耳を傾け対話しながら、熟成させてうまみを凝縮させていくんです。そして仕上げに、乾燥機で乾燥させて出荷します。水分量7~10%が理想ですね。
「丸干」をつくるこの仕事は、長く続く気仙沼の冬の風物誌。これからも江戸時代からの伝統をしっかり守り、受け継いでいきたいと思います。 -



TOYO TIRE株式会社 検査課 第二検査グループ
庄司光
製造するタイヤの品質をチェックするのが私たち検査課。検査課の厳しい検査をクリアしたものだけがTOYO TIRESの商品となり、お客さまの元に届けられます。そう考えると一層、身が引き締まる思いがします。
検査は、均一性を計測する「ユニフォミティー測定」や揺れと振動をチェックする「バランス測定」などを機械を使用して行ないます。でもこれで終わりではありません。タイヤは地面に接するトレッド部や側面のサイドウォール、タイヤをホイールにかみ合わせるビードなど様々な部材を組み合わせて製造されています。部位によって不具合が出やすいポイントが違うので、それを考慮した上で、機械では検出できないゴムの貼り合わせ部分の不具合や細微なバリ(突起)、キズがないかなどを、細かな検査項目に沿って人の目と手によって最終確認をします。
私自身はリーダーという立場なので、主に現場業務よりも検査ラインの管理をしています。検査するタイヤのサイズや種類が変わっていく中で、どのラインにどう流していくのか、いかに効率の良い人材配置にするかなどをコントロールしています。検査課の仕事は繊細な業務が多く集中力が必要。チーム内でのコミュニケーションを大切にし、作業員が集中して仕事ができる環境を整えることも、リーダーとして大切な仕事だと考えています。
仙台工場ものづくりムービー
ここ宮城から、世界に驚きと感動を届けたい。一本のタイヤに、技術と情熱のすべてを込めて。日々、新たな挑戦を続ける仙台工場の様子をご覧ください。