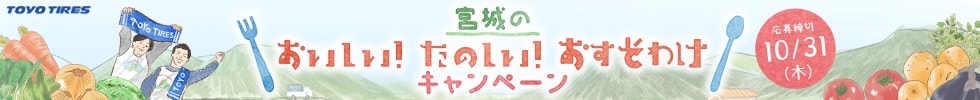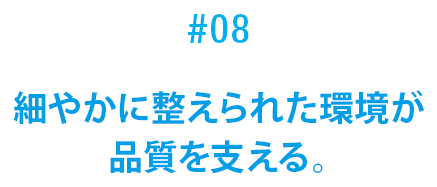-



宮城県栗原町 イワナ生産者
数又貞夫さん
きれいな水を好み、警戒心が強いイワナ。特に餌付けが難しく、養殖は不可能だと言われてきましたが、それを日本ではじめて成功させたのが、私の父。1969年のことでした。
その8年後に私も加わり、今日までの47年間、この栗駒耕英地区でイワナの養殖を続けてきていますが、万事順調というわけではありませんでした。2008年の岩手・宮城内陸地震では養魚施設が全壊、2011年9月の宮城豪雨では、翌年出荷予定だった稚魚3万匹のうち、1万匹が流れ込んだ濁流により酸欠状態になって死んでしまったことも。
大切なイワナを守るためには、天災も含めて天気・気候を読み、いかに環境を整えるかがポイントになります。そういう意味で、水の管理には特に気を遣いますね。水がイワナの質をにぎっている、といっても過言ではありません。近くを流れる川の水はアルカリ性が強く、イワナには合わないので、山から湧水を引き、水温を一年通して8~10℃に保つようにしています。またイワナは流水でなければ生きられないので、雨が降ったときは取水口に泥やゴミが詰まっていないかを夜中でもすぐに確認をして、常に新しい水が流れ込むように対応しています。24時間、365日、常にイワナを気にかけ、環境の手入れに漏れを作らないこと。それが秘訣です。
気が休まる時がありませんが、その分手塩にかけたイワナが成魚した時の喜びはひとしおです。 -



TOYO TIRE株式会社 保全課
第一設備グループ 千葉洋史
一見黒いゴムの輪っかに見えるタイヤ。しかし、実は十数種類の素材を混合・切り出し・加工して製造しており、工程ごとにいくつもの大型生産機械が導入されています。保全課では、これら工場内のすべての機械を正常に稼働させるためのメンテナンスを行なっています。
私が担当しているのは、天然ゴムやカーボンブラックなどの素材からタイヤの元となる“部材”を作り出す「精錬工程」。ここはタイヤづくりのスタート地点でいわば“要(かなめ)”です。機械が止まってしまったり、部材に不具合が起きてしまうと、その後の工程すべてに影響が出てしまい、生産性に関わってくる。迅速な修理調整が勝負となりますし、何より問題が発生する前に不具合を“潰しておく”計画整備が重要になります。
また、扱っている素材がゴムですから、温かいと柔らかく、冷たいと硬くなる特性に合わせて、季節に応じた機械の調整も求められますね。作業現場と綿密なコミュニケーションを取りながら、臨機応変にメンテナンスを行なっています。
万が一のことが起きないように、日ごろから細やかにチェックはしていますが、それでも突発的なことが起こることも。そんなときは業務時間外でも駆けつけるので、まるで外科医みたいだなと思っています(笑)。
生産設備のメンテナンスを通して、現場の生産作業を支えていることにやりがいを感じています。
仙台工場ものづくりムービー
ここ宮城から、世界に驚きと感動を届けたい。一本のタイヤに、技術と情熱のすべてを込めて。日々、新たな挑戦を続ける仙台工場の様子をご覧ください。